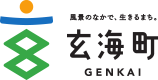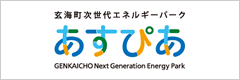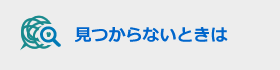本文
法定外公共物関係申請手続きについて
1.里道・水路、その上空や地下に施設を設置するなど、継続的に占用(使用)したいとき
法定外公共物について
道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法など管理の方法を定める法律の適用または準用がないものを法定外公共物(里道や水路など)といいます。法定外公共物の多くは、あぜ道や水路として自然発生的に形成され、地域住民等に使用されてきました。明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類され、国によって管理されていましたが、権限移譲により平成14年度に市町村が譲与を受けたものについては、市町村が「機能管理」と「財産管理」を行っています。利用者がいなくなり放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃します。このような機能を失った法定外公共物について、町は改めて機能回復等の整備は行いませんので、利用者で機能の保全をお願いしています。
「機能管理とは」利用者によって機能が保全されているもの(道や水路として現に利用されているもの)については、機能維持の範囲内で軽微な補修などを行います。その他、占用などの許可や違法行為に対する監督処分などを行います。
「財産管理とは」不動産としての土地の財産上の管理をいい、用途廃止、道路と民地との境界確定、譲渡などを行います。
法定外公共物占用許可申請に関する条件(里道・水路)
道路法や河川法などの適用を受けない里道や水路(法定外公共物)に、工作物や物件、施設を設置し継続して使用するときは法定外公共物占用許可申請の手続きが必要です。
占用につき、占用料が発生します。
占用許可期間が切れたとき、占用許可の里道・水路を損傷したとき、または占用を廃止するときは申請者自ら占用物件を撤去し、法定外公共物の原型復旧が必要です。
占用場所が里道・水路以外に余地がないこと。※個人の土地と里道や水路(法定外公共物)の境界が不明確な場合は、境界確認の手続きが必要になります。(申請者負担)
【その他の根拠法令】 玄海町法定外公共物の管理に関する条例 玄海町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
法定外公共物占用許可申請
法定外公共物(里道・水路)を占用(使用)したいとき (※新規)
法定外公共物(里道・水路)の占用許可申請
同意書を添付の上、申請書を提出してください。
法定外公共物占用許可の期間を更新したいとき
法定外公共物(里道・水路)の占用許可期間更新申請書
占用者の名義を変更したいとき
相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて届出をお願いします。申請がない場合、旧所有者に占用料金を請求することになりますのでご注意ください。
占用物の所有者の変更(地位の承継を届け出ようとする場合)
占用物の所有者の変更(権利の譲渡の承認を受けようとする場合) ※譲渡人と譲受人、連名での申請が必要です。
2.里道・水路の形状を変更する工事を行い、継続的に占用(使用)したいとき
法定外公共物行為について
法定外公共物の管理者以外の方が、里道や水路に関する工事を行うことをいいます。工事を行うときは、管理者と区長の承認が必要になります。
法定外公共物行為許可申請に関する条件(里道・水路)
占用は里道・水路に工作物を設置し継続的に使用することですが、法定外公共物行為許可は、管理者以外の者が里道・水路の形状を変更する工事を行うことで法定外公共物行為許可申請の手続きが必要です。
工事の発注・工事費は申請者負担となり、工事完了後は管理者の所有となります。
法定外公共物行為許可申請の手続きと隣接者の同意書、工事完了後に完了届の提出が必要です。
占用場所が里道・水路以外に余地がないこと。
※工事の内容によっては、占用許可申請が必要になります。
※区が行う場合は、町補助金があります。法定外公共物維持補修事業補助金交付のご案内
申請が必要な工事
- 里道の舗装、盛土による造成
- 水路の補修・U字溝敷設
- 車両を乗り入れるために、歩道や縁石を切り下げる工事
- 里道の法面を切り取ったり埋め立てたりする工事
- 里道の施設(ガードレール、標識、街路樹など)を撤去または移動する工事
法定外公共物行為許可申請
里道・水路の形状変更する工事を行い、継続的に占用(使用)したいとき
施工内容がわかる書類と同意書を添付の上、申請書を提出してください。 なお、工事完了後は、工事完了届出書を提出してください。
3.公衆用道路の通行を制限したいとき
通行規制について
公衆用道路の通行規制をしたいときは、道路交通法に基づく許可が必要です。
通行規制申請に関する条件
玄海町の公衆用道路(町)において工事やイベント、作業を行うために一時的に通行を制限したいときは、事前にまちづくり課へ協議をお願いいたします。
※地域活性化等を目的とした路上競技、イベント、ロケ撮影等は、道路交通に与える影響が大きく、様々な調整を要するため、十分な時間的余裕をもって事前相談を行ってください。
制限によっては、ゴミの収集車や市内巡回バス、通学路等のルートを変更する必要があるため、道路通行制限開始日の2週間前までに提出をお願いします。事前予告や予告看板の設置が必要になる場合があります。
申請が必要な行為
公衆用道路(町)における工事若しくは作業、祭礼行事、ロケーション、集団行進など
【制限内容】 全面通行止、車両通行止、片側交互通行、片側相互通行、その他(幅員減少等)など
許可を受ける基準
道路交通法上の「道路」でない場合、管轄の警察署に提出する規定の「道路使用許可」とは異なる手続きですが、工事などの活動によっては道路使用許可も必要になる場合があります。まちづくり課への申請書等の届出が不要であっても、所轄警察署長への道路使用許可申請が必要な場合がございますので必ず確認をお願いいたします。道路交通法第七十七条に基づく※「道路使用許可」が発行されましたら、写しをまちづくり課へ提出してください。