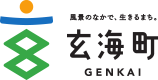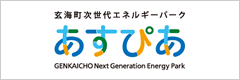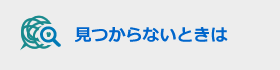本文
医療費が高額になったとき(国民健康保険)
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月21日更新
高額療養費について
医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻しを受けることができます。
「高額療養費」の払い戻しを受けるには、申請が必要です。
「高額療養費」の払い戻しを受けるには、申請が必要です。
70歳未満の人の場合
同じ人が、同じ病院で支払った自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻されます。
同じ世帯で、国民健康保険に加入している人は、同じ病院に21,000円以上の支払った自己負担額がある場合で、それらを合算して限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻されます。
同じ世帯で、国民健康保険に加入している人は、同じ病院に21,000円以上の支払った自己負担額がある場合で、それらを合算して限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻されます。
| 所得区分 | 適用区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|
| 基礎控除後の所得 901万円を超える |
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[140,100円] |
| 基礎控除後の所得 600万円を超え901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円] |
| 基礎控除後の所得 210万円を超え600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円] |
| 基礎控除後の所得 210万円以下 |
エ | 57,600円[44,400円] |
| 住民税非課税世 | オ | 35,400円[24,600円] |
基礎控除後の所得とは、総所得金額等(給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を引いたあとの所得)から基礎控除額(430,000円)を引いた額です。
[ ]内の金額は、過去12か月間に自己負担限度額を超える支払いが3回以上生じた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
[ ]内の金額は、過去12か月間に自己負担限度額を超える支払いが3回以上生じた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
70歳以上75歳未満の人の場合
1か月中に2回以上の通院がある場合は、自己負担分を合算して限度額表中「外来(個人単位)」の限度額を超えた分が払い戻されます。
同じ1か月中に通院・入院がある場合は、同じ世帯の70歳以上75歳未満の人の通院の自己負担分を合算して限度額表中「入院・世帯単位(外来+入院)」の限度額を超えた分が払い戻されます。
同一世帯に70歳未満の人の負担(21,000円以上)がある場合は、さらに合算して国保世帯の限度額(70歳未満の人の自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。
75歳の誕生月は「誕生日前の国民健康保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
同じ1か月中に通院・入院がある場合は、同じ世帯の70歳以上75歳未満の人の通院の自己負担分を合算して限度額表中「入院・世帯単位(外来+入院)」の限度額を超えた分が払い戻されます。
同一世帯に70歳未満の人の負担(21,000円以上)がある場合は、さらに合算して国保世帯の限度額(70歳未満の人の自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。
75歳の誕生月は「誕生日前の国民健康保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
| 所得区分 | 負担割合 | 適用区分 | 外来(個人単位) | 入院・世帯単位(外来+入院) |
|---|---|---|---|---|
| 課税所得 690万円以上 |
3割 | 現役並み3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
|
| 課税所得 380万円以上 |
3割 | 現役並み2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
|
| 課税所得 145万円以上 |
3割 | 現役並み1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
|
| 一般 | 2割 | 一般 |
18,000円 [年間144,000円] |
57,600円[44,400円] |
|
住民税非課税 |
2割 | 低2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税 (低所得1) |
2割 | 低1 | 8,000円 | 15,000円 |
課税所得とは、総所得金額等ー所得控除額(社会保険料、生命保険料などの控除額の合計)を引いた額です。
[ ]内の金額は、過去12か月間に自己負担限度額を超える支払いが3回以上生じた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
所得区分が一般で、年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合は、高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
低所得2とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の人です(低所得1を除く)。
低所得1とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。
[ ]内の金額は、過去12か月間に自己負担限度額を超える支払いが3回以上生じた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
所得区分が一般で、年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合は、高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
低所得2とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の人です(低所得1を除く)。
低所得1とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)<外部リンク>
限度額適用認定証等について
高額療養費の払い戻しまでの一時的な負担を軽減するために、限度額適用認定証等があります。限度額適用認定証等を病院や薬局などの窓口で提示することで、医療費の支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。
【マイナ保険証を利用ください】
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続き(申請)なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。以下の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。
ただし、長期(90日を超える)入院該当の場合は申請が必要です。
また、国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関で認定区分が確認できない場合があります。
【マイナ保険証を利用ください】
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続き(申請)なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。以下の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。
ただし、長期(90日を超える)入院該当の場合は申請が必要です。
また、国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関で認定区分が確認できない場合があります。
認定証の種類
・限度額認定証
病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療・食事代を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額されます。
・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人が対象)
病院の窓口で提示すると、入院中の食事代(標準負担額)が減額されます。
・限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人が対象)
病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額され、食事代(標準負担額)も減額されます。
病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療・食事代を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額されます。
・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人が対象)
病院の窓口で提示すると、入院中の食事代(標準負担額)が減額されます。
・限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人が対象)
病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額され、食事代(標準負担額)も減額されます。
申請方法
役場窓口で申請書を提出してください。
世帯に税の未申告の人がいる場合や国民健康保険税に滞納がある場合などは、認定証を交付できないことがあります。
70歳以上の住民税課税世帯の人で、課税所得が145万円未満または690万円以上の人(適用区分が低1、低2、現役並み1、現役並み2のいずれにも当てはまらない人)は、交付申請は不要です。
・世帯主と交付を受ける人のマイナンバーがわかるもの
・窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・委任状(別世帯の人が申請するとき)
・住民税非課税世帯で過去12カ月間の入院日数が90日を超える場合は、⼊院⽇数が確認できる書類(領収書など)
世帯に税の未申告の人がいる場合や国民健康保険税に滞納がある場合などは、認定証を交付できないことがあります。
70歳以上の住民税課税世帯の人で、課税所得が145万円未満または690万円以上の人(適用区分が低1、低2、現役並み1、現役並み2のいずれにも当てはまらない人)は、交付申請は不要です。
・世帯主と交付を受ける人のマイナンバーがわかるもの
・窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・委任状(別世帯の人が申請するとき)
・住民税非課税世帯で過去12カ月間の入院日数が90日を超える場合は、⼊院⽇数が確認できる書類(領収書など)
高額な外来診療を受ける皆さまへ(厚生労働省)<外部リンク>
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関などの窓口に提示することで、自己負担限度額が1か月10,000円(人工透析をしている慢性腎不全の人で70歳未満の所得区分ア、イの人は1か月20,000円)になります。
申請方法
役場窓口で申請書を提出してください。
・世帯主と交付を受ける人のマイナンバーがわかるもの
・窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・委任状(別世帯の人が申請するとき)
・医師の証明(前健康保険で発行された特定疾病療養受療証でも可。)
・世帯主と交付を受ける人のマイナンバーがわかるもの
・窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・委任状(別世帯の人が申請するとき)
・医師の証明(前健康保険で発行された特定疾病療養受療証でも可。)
一部負担金減免等について
災害等により、資産等に重大な損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したことなどにより、医療機関等の窓口で、一部負担金の支払いが困難となったときは、申請により一部負担金の支払いの減額や免除、猶予ができる場合があります。
詳しくは国民健康保険担当までご相談ください。
詳しくは国民健康保険担当までご相談ください。