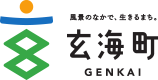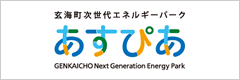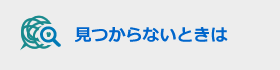本文
瑞花双鳳八稜鏡
印刷用ページを表示する更新日:2025年10月2日更新
瑞花双鳳八稜鏡
平成7年(1995)に行われた長倉遺跡発掘調査では、弥生時代の石棺墓や鎌倉時代の遺構などが検出され、本鏡は鎌倉時代の可能性がある石敷遺構上より出土した銅鏡です。
面径9月1日~9.2 cm、縁高0.5 ~0.6 cm、重さ147.5gです。外縁及び内縁の形態は八弁菱花形をしています。
鏡背は急斜へ字圏によって内外区に分け、内区では花芯座紐を中心として上下に瑞花を左右に3条の尾をもつ2羽の鳳凰がそれぞれ対置されてます。一方、外区には珠文によって草花状のものが表現されています。また、内区中央の紐は直径0.9 cm、高さ0.3 cmの素縁紐で、紐は楕円形に大きく広がっています。紐部分のみ、後に空けたとも考えられます。
本鏡は様式形態より平安時代末期~鎌倉時代初頭に想定される和鏡ですが、伝世品、または踏み返し鏡かは不明です。当時、日本では銅が不足していたことから、鏡制作に鉛含有量の多い宗銭を鋳直したとされています。本鏡も鉛の含有量が41.4~53.3パーセントと非常に高く、「鉛銅手」と呼ばれる鉛含有量の多い粗鏡といえますが、当時の事情をよく示しています。本鏡は、佐賀県内から出土した八稜鏡のうち唯一完形で出土したものです。平成9年度に、防錆処理並びに強化処理を行っています。
面径9月1日~9.2 cm、縁高0.5 ~0.6 cm、重さ147.5gです。外縁及び内縁の形態は八弁菱花形をしています。
鏡背は急斜へ字圏によって内外区に分け、内区では花芯座紐を中心として上下に瑞花を左右に3条の尾をもつ2羽の鳳凰がそれぞれ対置されてます。一方、外区には珠文によって草花状のものが表現されています。また、内区中央の紐は直径0.9 cm、高さ0.3 cmの素縁紐で、紐は楕円形に大きく広がっています。紐部分のみ、後に空けたとも考えられます。
本鏡は様式形態より平安時代末期~鎌倉時代初頭に想定される和鏡ですが、伝世品、または踏み返し鏡かは不明です。当時、日本では銅が不足していたことから、鏡制作に鉛含有量の多い宗銭を鋳直したとされています。本鏡も鉛の含有量が41.4~53.3パーセントと非常に高く、「鉛銅手」と呼ばれる鉛含有量の多い粗鏡といえますが、当時の事情をよく示しています。本鏡は、佐賀県内から出土した八稜鏡のうち唯一完形で出土したものです。平成9年度に、防錆処理並びに強化処理を行っています。