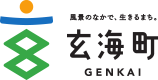本文
玄海町地名のおこり
印刷用ページを表示する更新日:2025年8月26日更新
玄海町地名のおこり
玄海町(げんかいちょう)
「玄」は「暗い・黒い」という意味があります。 「海」は玄界灘を省略したものです。つまり、「玄海」は「くろい海」という意味です。
町名は、東松浦半島の前面に広がる海「玄海」には常に対馬暖流が流れ、(1)古来大陸文化の流入する海、(2)豊かな海の幸、(3)海洋性気候のもたらす豊富な陸産物、(4)太古の時代阿蘇山噴火でできた玄武岩塊の連なる海岸、(5)丘陵の景勝地、これら5つの特徴を地盤として、さらに将来に向け大発展を願う期待をかけて付けられました。
本町は、古くは『魏志倭人伝』の末盧国の一部になります。町制施行前の値賀、有浦の二村の名は共に古くから存在しました。値賀の名は南北朝期の『有浦家文書』の佐志淨覚(じょうかく)挙譲状案(1313年)」に「肥前國松浦郷庄値賀村田地屋」とあります。有浦の名は同文書の佐志勤譲状案(1342年)に「肥前國松浦郷庄佐志村内有浦今里村」があります。
中世戦国時代は、松浦党の一族、値賀氏、有浦氏の居城地でした。その後は唐津藩領となりました。
町名は、東松浦半島の前面に広がる海「玄海」には常に対馬暖流が流れ、(1)古来大陸文化の流入する海、(2)豊かな海の幸、(3)海洋性気候のもたらす豊富な陸産物、(4)太古の時代阿蘇山噴火でできた玄武岩塊の連なる海岸、(5)丘陵の景勝地、これら5つの特徴を地盤として、さらに将来に向け大発展を願う期待をかけて付けられました。
本町は、古くは『魏志倭人伝』の末盧国の一部になります。町制施行前の値賀、有浦の二村の名は共に古くから存在しました。値賀の名は南北朝期の『有浦家文書』の佐志淨覚(じょうかく)挙譲状案(1313年)」に「肥前國松浦郷庄値賀村田地屋」とあります。有浦の名は同文書の佐志勤譲状案(1342年)に「肥前國松浦郷庄佐志村内有浦今里村」があります。
中世戦国時代は、松浦党の一族、値賀氏、有浦氏の居城地でした。その後は唐津藩領となりました。
有浦(ありうら)
「有浦」という地名は、『玄海町史・上巻』によると、地形から生まれた地名です。
江戸時代以前の有浦地域は、仮屋湾が深く陸地に入りこみ、今の長倉の集落あたりは犬吠川、下村川、上村川、有浦川などが流れ込む海岸でした。これに目をつけた唐津初代藩主・寺沢広高は、この海岸に干拓事業を始め、今の有浦新田の陸地ができ、この「山あい(相、合う)の浦」が訛(なま)って、「ありうら」の呼称になったと考えられています。
また、地元には、有浦川周辺の地形が蟻(あり)の行列に似ていることから地名になった、との説もあります。
江戸時代以前の有浦地域は、仮屋湾が深く陸地に入りこみ、今の長倉の集落あたりは犬吠川、下村川、上村川、有浦川などが流れ込む海岸でした。これに目をつけた唐津初代藩主・寺沢広高は、この海岸に干拓事業を始め、今の有浦新田の陸地ができ、この「山あい(相、合う)の浦」が訛(なま)って、「ありうら」の呼称になったと考えられています。
また、地元には、有浦川周辺の地形が蟻(あり)の行列に似ていることから地名になった、との説もあります。
値賀(ちか)
「値賀」という地名は、『値賀史』によると、「値嘉島(長崎県五島諸島)の中の小値賀島(現長崎県北松浦郡)を領土としていた値賀氏の祖先が、この地名にちなんで値賀氏と称していました。その値賀氏の別家が玄海町に上陸して、値賀地域の支配権を握りました。その支配者の姓がそのまま値賀の地名になった、と伝えられています。
すなわち、地名(小値賀島)が姓(値賀十郎)となり、その姓が新たに地名(値賀村)となったようです。
すなわち、地名(小値賀島)が姓(値賀十郎)となり、その姓が新たに地名(値賀村)となったようです。
小加倉(こがくら)
小加倉の「かくら(加倉)」は、小集落や狩り場の意味があり、狩り場のことを「かりくら(狩倉)」とも言います。小加倉は「かつてこの地を治めていた領主の小さい狩り場であった。」ところから地名が付けられたと考えられます。
有浦下(ありうらしも)
有浦下の「ありうら(有浦)」は、「山あいの浦」が訛って地名になったと言われています。「しも(下)」は方向や位置などにおいて下の方を意味しています。かつては、現在の有浦上、下の集落一帯を有浦と呼ばれ、その有浦の内で、西側に位置する集落なので「有浦下」と呼ばれるようになったと考えられます。
有浦上(ありうらかみ)
有浦上の「かみ(上)」は、方向や位置などにおいて上の方を意味しています。かつては、現在の有浦上、下の集落一帯を「有浦」と呼称され、その「有浦」の内で、東側に位置する集落を、「有浦上」と呼ばれるようになったと考えられます。
長倉(ながくら)
長倉の「なが(長)」とは長いことの意味で、地形、器、生物などを修飾するほか、首長の「オサ」の意味があります。「くら(倉)」は入りくんで、崖や谷などの多い地形の語源です。長倉は「入りくんだ長い谷間の中にある」ということから地名が付けられたと考えられます。
また、「くら」を蔵、倉庫の意味で、かつて集落付近まで海岸であったと伝えられていることから、大きな(長い)倉または倉が長く連なっていたと想像され、そこから地名が付けられたとも考えられます。
また、「くら」を蔵、倉庫の意味で、かつて集落付近まで海岸であったと伝えられていることから、大きな(長い)倉または倉が長く連なっていたと想像され、そこから地名が付けられたとも考えられます。
諸浦(もろうら)
諸浦の「もろ(諸)」は、「ムラ(村)」の訛りで、「うら(浦)」は湾、入り江、海岸を意味しています。入り江の中にある村ということで、地名が付けられたと考えられます。
新田(しんでん)
新田は、今から400年前の江戸初期に、唐津藩主寺澤志摩守が有浦川下流を干拓して「新しい新田を造った集落」から呼ばれるようになったと伝えられています。【1622(元和8)年に新田完成】
牟形(むかた)
牟形は、仮屋湾奥の海岸沿いにあり、海岸は遠浅で入り江になって、干潮のときは潟が広がります。「むかた(牟形)」の地名は「むた(牟田)」と「かた(潟)」を合わせて「むたがた(牟田潟)」が「むかた(牟形)」になったと考えられます。牟田は湿地や沼地のことを意味し、かた(形)はかた(潟)の当て字と思われ、潟は海岸の遠浅や浦、入り江の意味があります。このことから、「入り江と干潟の景観」から付けられたと考えられます。
轟木(とどろき)
轟木には、「川や滝のとどろく音、馬や車輪の音の響きなどからちなむ」という地名の語源があります。集落は、地理的に上場台地の上にあり、集落の東部から北部にかけての谷間には有浦川と支流の受付川が流れています。この川は小川ですが急傾斜で流れが激しいので、静かな集落に水の音が「とどろいていた」ところから轟木と呼ばれるようになったと考えられます。
大鳥(おおとり)
大鳥は、1945(昭和20)年5月大鳥集落の発足祝賀会があり、当時の有浦村長が、大きい鳥(集落の土地の形が「鳥の形」に似ている)が羽ばたくように、集落が将来大きく羽ばたくことを願って、命名したと伝えられています。
座川内(そそろがわち)
座川内には岩山が多く点在し、しかも急傾斜で落石しやすく、山の谷間に川が流れているところから「座川内」と付けられたと考えられます。
急に崩れ落ちる意味の語源からきている「ざ(座)」を「そそろ」と当て、河川の意味の「かわち(川内・河内)」を合わせて「そそろがわち」と呼び、「坐川内」または「座川内」と記すようになったと考えられます。
急に崩れ落ちる意味の語源からきている「ざ(座)」を「そそろ」と当て、河川の意味の「かわち(川内・河内)」を合わせて「そそろがわち」と呼び、「坐川内」または「座川内」と記すようになったと考えられます。
湯野尾(ゆのお)
湯野尾には「ゆ(湯)」が出ていたところがあったと伝承があり、「ゆ(湯)は温泉のゆ(湯)」の意味。「の(野)」は「緩やかな傾斜地や丘」を意味し、「お(尾)」は「稜線、丘などの高い所、山の尾根」の意味です。
地名は「湯が集落を囲む山の尾根から出ていた」ところから付けられたと考えられます。
地名は「湯が集落を囲む山の尾根から出ていた」ところから付けられたと考えられます。
田代(たしろ)
田代は「田のしろ(料)」で稲の意味があります。集落には、約450年前の元亀年間(1570~73年)に佐志の農民7人が来て、この地なら稲が作れるだろうと移住したのが始まりであるという伝えがあります。
集落は、浅い盆地の中にあり、中央部に河川が流れ、一帯は湿地地帯で、稲作に適した場所でした。地名は湿地を水田に開発し、稲の取れるよう開発新田したところから「田代」と呼ばれるようになったと考えられます。
集落は、浅い盆地の中にあり、中央部に河川が流れ、一帯は湿地地帯で、稲作に適した場所でした。地名は湿地を水田に開発し、稲の取れるよう開発新田したところから「田代」と呼ばれるようになったと考えられます。
藤平(ふじひら)
藤平の「ふじ(藤)」は、藤の生えているところや傾斜地などの意味があり、「ひら(平)」は山中の広い傾斜面、平らなところなどの意味です。かつて、集落の山々に「藤」の花が咲いていたから「藤」の付く地名ができたと考えられ、「山河に多くの藤の花が咲いている集落」ということで、「藤平」と呼ばれるようになったと考えられます。
また、一説に神功皇后が朝鮮半島遠征の折に「藤平官者(ふじひらかんじゃ)」という陶工を連れてきて、当地に住んだので、「藤平」と呼ばれるようになったという伝えもあります。
また、一説に神功皇后が朝鮮半島遠征の折に「藤平官者(ふじひらかんじゃ)」という陶工を連れてきて、当地に住んだので、「藤平」と呼ばれるようになったという伝えもあります。
値賀川内(ちかがわち)
値賀川内の「川内(河内)」は河川の意味があります。値賀に流れている川の流域に地区があることから地名が付けられたと考えられます。
仮立(かりたち)
仮立の「たち(立)」は城、砦などを意味します。集落の北の「城ノ山」は「かつて値賀郷を治めていた値賀氏の城でした。さらに、城は近世の城と違い、戦いのときだけ使用した砦のようなもの」と伝えられています。地名は仮の城から「仮立」と付けられたと考えられます。
中通(なかどおり)
中通の「なか(中)」は中央とか中間の意味で、「とおり(通)」とは新しくつくられた村や田の道筋の意味があります。当時、佐志一族がこの値賀村一帯を治めていたころ、産土神として祀っていた今岡権現(値賀神社)へ佐志から来るときや、値賀村の産物を外津浦の置場まで運ぶときなどの道筋であったと推測されます。
地名は『値賀の中心の通り』ということから「中通」と付けられたと考えられます。
地名は『値賀の中心の通り』ということから「中通」と付けられたと考えられます。
下宮(しもみや)
下宮の「しも」は「し(下)」「も(方)」という語源があり、「みや(宮)」は神を祀(まつ)る建物を意味することから、集落の西側の丘陵地に氏神の値賀神社があり、神社から集落をみると「下の方に位置する集落」から「下宮」と地名が付けられたと考えられます。
外津(ほかわず)
外津の「ほか(外)」は「はずれ」の意味で、「わず」は「はず」のことで「津(つ)」の文字をあて、「果て、はずれ、港や泊まり」の意味があります。すなわち、「浦のはずれか、地域のはずれにある港」から「ほかわず(外津)」と呼ぶようになったと考えられます。
普恩寺(ふおんじ)
普恩寺は、集落内に古くからあった普恩寺(創建は南北朝期)という寺の名前が、「いつからとなく集落の名称になった」と伝えられています。
平尾(ひらお)
平尾の「平(ひら)」は「平らな土地とか山中の小さな平地」、「尾(お)」は「丘などの高い所、山の峰」などの意味があります。集落は上場台地(海抜約75m)の上にあり、一帯は平らな丘陵地になっているところから、「平尾」と付けられたと考えられます。
浜野浦(はまのうら)
浜野浦の「はま(浜)」は、海岸、河岸の意味として多く使われますが、本来は、崖とか急傾斜になっている岸の意味が転じて、崖や急傾斜でない岸のことをいいます。
「うら(浦)」は湾や入り江、海岸で、「の(野)」は緩やかな丘や傾斜地の意味です。浜野浦の地名は急傾斜になっている海岸、緩やかな丘、入り江のある集落ということで付けられたと考えられます。
「うら(浦)」は湾や入り江、海岸で、「の(野)」は緩やかな丘や傾斜地の意味です。浜野浦の地名は急傾斜になっている海岸、緩やかな丘、入り江のある集落ということで付けられたと考えられます。
大薗(おおぞの)
大薗の「その」には「薗」「園」「苑」などが当てられ、菜園や果樹園などの意味で、「その(園)」は果樹の畑、垣根のある畑の意味があります。地名は集落が台地の西斜面に位置し、その一帯は冬の季節風を遮るものがないので田畑の周りに防風のため、萱(かや)や笹が植えられ、田畑の垣根にしていたところから地名が付いたと考えられます。
石田(いしだ)
石田には「文禄・慶長の役(1592、1597年)」のとき石田三成がこの地にきて野菜を作らせたとか関ヶ原の合戦(1600年)で敗れた石田軍の兵士が、逃げてきて住み着いたので石田の地名が付いた」との伝承があります。しかし、文禄・慶長の役以前、1342年付「佐志勤譲状案」(有浦家文書)に「石田海夫助次郎一類等」とあるので、「石田」の地名がすでに存在していたと思われます。
別説として、全国に点在している「いしだ(石田)」の中に、地名の起こりとして「地質の固い田」のところから付けられたとあり、石田一帯も台地上や斜面にあり、地質も比較的固いので、同様にも考えられます。
別説として、全国に点在している「いしだ(石田)」の中に、地名の起こりとして「地質の固い田」のところから付けられたとあり、石田一帯も台地上や斜面にあり、地質も比較的固いので、同様にも考えられます。
花の木(はなのき)
花の木は「野花がよく咲いた原野があったことから地名が付いた」と伝えられています。また「はな(花)」は「先端」の意味もあり、花の木は石田の本集落より、地理的に高い位置にあり、集落の東側から南側にかけては高い崖で「木の突端は高いところ」にあり、方言で「突端のところ」を「はなんにき」と言われているのが訛って地名ができたとも考えられます。
仮屋(かりや)
仮屋には、藤原広嗣が740(天平12)年、板櫃の戦いで敗戦し、西走したときにこの地に来て病になり、住人が「仮屋」(仮小屋)を建てて介抱したことにちなんで地名が付けられたと言われています。
栄(さかえ)
栄は、1946(昭和21)年に入植者の投票により名称が付けられました。栄とは集落が将来にわたって栄えてほしいとの意味があります。
シーラインタウン(普恩寺)
地名ではありませんが、行政区名であるシーラインタウン(町営住宅)は、公募により「高台から水平線が見える」の意味から名付けられました。