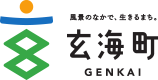本文
木造聖観音菩薩坐像
印刷用ページを表示する更新日:2019年3月7日更新
平成8年5月29日県指定重要文化財
普恩寺の本尊として伝わっています。南北朝時代の作品で、胎内の銘文から暦応5年(北朝年号・1342)に松浦党(まつうらとう)の人々を檀那(だんな)とし、九州に数例の作品を残す慶派(けいは)系統の仏師湛勝(たんしょう)によって製作されました。像高は57cm。ひのき材による寄木造りで、眼には水晶をはめて、身や着衣はうるしを塗って金箔をはっており、保存状態はすぐれています。宝冠(ほうかん)・持物(じもつ)・髻(もとどり)は後世に補修されています。
この観音像の造像には松浦党の人々が関連しており、また、製作の年、製作者がわかり、彫刻史や中世松浦党の研究を進めていく上からも貴重な資料です。
普恩寺の本尊として伝わっています。南北朝時代の作品で、胎内の銘文から暦応5年(北朝年号・1342)に松浦党(まつうらとう)の人々を檀那(だんな)とし、九州に数例の作品を残す慶派(けいは)系統の仏師湛勝(たんしょう)によって製作されました。像高は57cm。ひのき材による寄木造りで、眼には水晶をはめて、身や着衣はうるしを塗って金箔をはっており、保存状態はすぐれています。宝冠(ほうかん)・持物(じもつ)・髻(もとどり)は後世に補修されています。
この観音像の造像には松浦党の人々が関連しており、また、製作の年、製作者がわかり、彫刻史や中世松浦党の研究を進めていく上からも貴重な資料です。

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>